「墨攻」というマンガを原作とする映画がありました。
あの作品に登場する墨家は実在の団体であり、古代中国において大きな影響力を持ちました。
戦国時代に活躍し、墨子を首領とし、きわめて特殊な行動規範をもった興味深い団体です。
その主張を次の3つにまとめます。
・兼愛
・非攻
・節葬
それぞれについて説明していきます。
兼愛
愛に差別を設けない。
親だから、子だから、妻だから、友人だから。
そうではなく、そのような区別を捨てて、お互いに愛さなければならない。
それが「兼愛」です。
きわめて特殊な主張で、中国思想史のなかでも特異なものです。
よくキリスト教の隣人愛に比較されますが、それほど中国の伝統のなかでは比較する対象がみつからないほど奇妙なものなのです。
「幇」という視点
中国人の行動原理についての鋭い指摘で知られる小室直樹によれば、中国人は血のつながりである「宗族」と義のつながりである「幇」、この二つの原理で動くと書いています(小室直樹の中国原論」)。
この説で墨子の主張を見てみると、兼愛はあきらかに「幇」の原理の適用です。
「幇」は、血のつながりではなく義で他人と結びつきます。
ひとたび、この「幇」のつながりを持てば、もはや他人は他人ではありません。
肉親と同等、いやそれに匹敵する共同体となるのです。
小室直樹はその説明として「三国志」の関羽をエピソードを挙げています。
関羽が曹操に捕らわれ、才能を惜しんだ曹操によって破格の待遇を受けたにもかかわらず、劉備のもとに去ったエピソードです。
劉備と関羽は義兄弟、つまり「幇」の関係だったため、曹操がいかに関羽を厚遇しようとも、関羽は劉備を裏切りませんでした。
墨子は、天下の人々をして「幇」にしなければならないと考えていたのではないかと思います。
そう解釈すれば、墨子の主張は中国思想史のうえで特殊なものとは言えなくなります。
むしろきわめて中国人的な発想といえるでしょう。
ただし、墨子が「幇」を主張することはあっても、「宗族」を強調することはありません。
この辺に、墨家という集団の謎を解く鍵がありそうです。
墨家を構成する人たち
墨家は、「宗族」の保護を受けられない孤独な弱い立場の人々の集まりだったのではないかということです。
血のつながりというタテの連携ができないからこそ、「幇」という横のつながりを強固にするしかなかったのではないでしょうか。
墨家という集団が、戦国時代が終わり、漢帝国が樹立して社会構造が確定してくるにつれて消滅していったのも、そういう理由が背景にあるのでしょう。
兼愛は、墨家にとって必然的な主張だったのです。
非攻
天下を「幇」にするべく奮闘する墨家にとって、兼愛とともに非攻は、主張の両輪ともいうべきものです。
分け隔てなく愛することを主張するなら、争わないことに言及するのは論理的必然です。
他国を攻めるべきではない、と主張する人は珍しくありません。
昔も今も、そう主張する人は多い。
ですが、墨子のように行動に移す人はきわめて少ない。
この点は昔も今も変わるところはありません。
戦争のプロとしての墨子
しかも、墨子はただの口舌の徒ではありません。
いわば、戦争のプロです。
攻城戦の専門家でもあります。
戦争があれば、攻められた国に助力し、攻め手を退ける実力をもつ軍事集団です。
「墨守」という言葉はここからきています。
しかも軍事に訴えるのは最終手段です。
その前には墨子みずから軍を動かそうとする王のもとへ出向き、説得しようとするのです。
「公輸篇」には、楚王を説得する墨子の姿が描かれています。
そして、戦争を回避させた墨子の功績を知らずに、墨子を「冷遇する一般人の姿もまた描かれています。
本当のピースメーカーは正当に評価されることがありません。
節葬
葬儀を盛大に行うのが、古代の共通した習わしです。
そして、葬儀は簡素であるべきだ、という主張もまた葬儀とともに古くからあるのです。
墨子は簡素を旨とします。
彼ら墨家が「幇」の集団であり、「宗族」とは無縁の存在であるとするならば、当然の帰結です。
こまごまとした葬送の儀礼は、まさに「宗族」のものだからです。
そこで重要になるのは、序列です。
それは、社会を血の濃淡によって階層に分節することを意味します。
兼愛を主張する墨子とは相容れない所以です。
理想の葬儀とは
では、墨子が理想とする葬儀とはどういうものでしょうか。
日本には年老いた親を山に捨てる姥捨て山の伝説がありましたが、墨子はそのような方法を良しとするわけではありません。
悲しみにも節度が必要だ、というのが墨子の主張です。
厚すぎるのも、薄すぎるのも、ともに間違っているのです(節葬篇)。
墨子の主張は、現代に生きる私たちにとっても一つの参考になります。
墨家は滅びましたが、彼らの思想がまだ滅びていないのは、そこに有効性があるからでしょう。
まとめ
墨子は長い間、中国では顧みられなかった書物です。
ですが、墨子に目を通してみると、案外わたしたちにとって身近な存在であるのに驚くと思います。
孫子がいまなお、あたらしい解釈とともに読まれているのと同じく、墨子もまた、さまざまな角度から研究されるべき深みを持っている古典といえるでしょう。

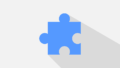

コメント