毛沢東の「実践論」について自分なりにまとめてみたい気持ちは若いころから持っていました。
現在では、毛沢東に熱狂する輩はまず皆無でしょうが、かつては絶大な影響力を持っていたようです。
私ごとですが、父親の本棚に文庫本の「実践論・矛盾論」を発見したときは少なからず驚いたものです。おそらく学生時代に買ったものでしょう。まったくのノンポリと思っていた父が毛沢東の文庫本を処分せず本棚に取っておいたことに驚いたのです。
そういう時代の空気も想像しつつ、毛沢東の「実践論」を読んでいきます。
「実践論」とは

「実践論」は毛沢東(1893~1969)の主著のひとつで、1937年7月に行われた講演をもとにしています。
書名のとおり「実践」の重要性を強調した内容となっていますが、あえて「実践」を仰々しく主張しなければならなかった背景には、当時の中国共産党内部の権力争いが関係しています。
具体的には博古(1907~1946)や王明(1904~1974)などソ連留学組の追い落としを狙ったものです。
当時の中国共産党はソ連の強い影響下にあり、そのためソ連留学組が中国共産党内で幅をきかせるのは自然の勢いでした。
毛沢東はソ連留学どころかそもそもソ連に信用されていない指導者でしたので、党内における最大の政敵がソ連留学組だったわけです。
彼ら留学組の強みは、革命の本場であるソ連で学んだマルクス主義理論でした。早い話が口喧嘩で一番強いということです。
毛沢東が党内の主導権を握るには、留学組を理論的に打破する必要があります。そのための理論的支柱が「実践論」と「矛盾論」です。
理論ではなく「実践」を強調した点がそのことをよく物語っています。
身も蓋もない話ですが、理論の精緻さにおいては留学組にはかないません。毛沢東が採用する戦術としては、その理論が現実と接点をもたない観念論にすぎないことを主張し、留学組の権威を失墜させることで党内の主導権を握ろうとしたのです。
毛沢東の作戦は奏功し、留学組は徐々に実権を失っていきました。
「実践論」「矛盾論」は理論闘争の書でもあるのです。自己表現のための書ではありません。権力奪取のための政治的パンフレットなのです。
実践とは何か
では、毛沢東が主張する「実践」とは何か、くわしく見ていきましょう。
「実践」という言葉で私たちは日常的な経験を連想します。何かをやってみる、あるいは本やネットで知った知識を実際に試してみる、そういうことです。
毛沢東のいう「実践」も私たちの日常経験とそれほど差があるわけではありません。
ただ、毛沢東はあくまで共産主義者を標ぼうしています。マルクス主義の文脈のなかで「実践」を語らなければなりません。
しかも、ソ連留学組に対する政治的パンフレットである「実践論」は、理論的認識の重要性は認めつつも「実践」を認識の上位に位置づけなければ意味がありません。
毛沢東は書いています。
認識あるいは理論が真理であるかどうかの判定は、主観的にどう思うかで決まるのではなく、社会的実践の結果が客観的にどうであるかによって決まる。
毛沢東 「実践論」
いくら理論に習熟していても意味はない。革命を成就させてこそ本物なのだ。
そう主張する毛沢東の傍らで苦虫をかみつぶしたような留学組の表情が浮かんでくるではありませんか。
では、以下で少し毛沢東の議論に付き合ってその細部を見ていきたいと思います。
意外に常識的な内容ですので、私たちの日常経験に照らしてうなづく点が多いのです。
つまり、毛沢東の「実践論」はマルクス主義の仮面をかぶったただの常識論でもあるともいえます。
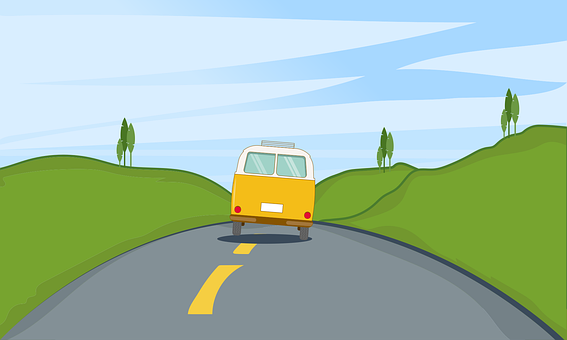
認識には段階がある
「認識」には段階がある、それが毛沢東の主張です。
「感性的認識」から「論理的認識」へと低い段階から高い段階へ、あるいは浅い段階から深い段階へと変位していく、というのがその内容です。
感性的認識から論理的認識へ
「感性的認識」とは、「感覚と印象の段階」です。
これは旅行客の観光を考えればわかりやすいでしょう。
ガイドに案内され有名な観光地を巡り、風光明媚な景色に感動し、その土地の名物に舌鼓を打つ。
まさに「感覚と印象の段階」です。
この段階では、まだ、人々は深い概念を組み立てることも、論理のとおった結論をひきだすこともできない
毛沢東「実践論」
では、概念はどのように生まれるのでしょうか。結論からいえば「飛躍」によって生まれます。
社会的実践の継続によって、人々にその感覚と印象をひきおこしたことがらが、実践のなかで、何回となくくりかえされる。すると、人々の頭のなかで、認識過程における突然の変化が起こり、概念が生みだされる。
毛沢東「実践論」
つまり、「量」から「質」への転換です。
一定の閾値を超えたときにおこる現象です。
それが「飛躍」です。
概念を用いた思索が稼働しはじめるのです。
しかし、「論理的認識」が「感性的認識」の高次にあるとはいえ、あくまで基礎となるのは「感性的認識」であることに留意しなければなりません。
「梨の甘さを知りたければ、かじってみなければならない」からです。
客観的認識を使って世界を改造する
毛沢東は書いています。
人間は万事を直接に経験するわけにはいかない。
毛沢東「実践論」
個人には時間も能力も限界があります。
「感性的認識」が基礎なのはその通りですが、実際の仕事では「感性的認識」だけに頼るわけにはいきません。概念による「論理的認識」の経験が不可欠です。
認識に段階がある以上当然ですが、実践者は概念を駆使して組織化・計画化を通じて理論を実現していかなければなりません。
ここで重要な役割を果たすのは「論理的認識」です。レーニンがいうように、「革命的理論なくしては革命的運動もない」のです。
認識に完成はない
しかし、これでは「実践」は「論理的認識」にいたるための方法論にすぎないのではないか。
実際、「実践」とはそういうものですが、毛沢東にとっては都合が悪いのではないか。「論理的認識」ではマルクス主義を本場で学んだソ連留学組にかなわないでしょうから。
そこで重要になるのは、認識に完成はない、という観点です。
まず初めに「感性的認識」があり、これを繰り返すことで「論理的認識」が生まれ、この「論理的認識」をもとに社会改造を行い認識をさらに深め、ふたたび「実践」に戻っていく。らせん状に深まり行く認識を想定するのです。まさに永久革命です。
ただ、毛沢東も書いていますが、日常の仕事を振り返ってみても私たちは数多くの失敗を経験することで仕事に習熟していきます。もちろん完成ということはありません。
このことは個人個人の経験のうえでは真理ですが、国家がこの理屈を盾にとって人民に押し付けてくるとなるとどうでしょう。
ブラック企業どころではありません。全体主義国家の完成ということになってしまいます。
その意味で、毛沢東は注意を要する人物であると思うのです。個人にのみ適用できる論理を全体におし及ぼす危険性。毛沢東を読むときはこの点に注意が必要なのではないでしょうか。
DMM.com証券


コメント
[…] 毛沢東の「実践論」を読む […]